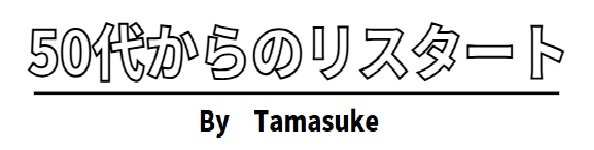こんにちは!今日は4月1日、そう、エイプリルフールですね!皆さんは今日、誰かにいたずらをしましたか?それとも、されましたか?
実は、この「嘘をついてもOKな日」には、意外と深い歴史があるんです。今日はエイプリルフールがなぜ始まったのか、世界各国ではどう楽しまれているのかをサクッと紹介していきます!
エイプリルフールって、そもそもどこから来たの?
エイプリルフールの起源には、いくつかの説があります。最も有力とされているのは、16世紀のヨーロッパで暦が変わったことに関連する説です。
昔、ヨーロッパの多くの国では3月25日頃から新年のお祝いが始まり、4月1日まで続いていました。ところが、1500年代にグレゴリオ暦が導入されると、新年は1月1日に変更されたんです。
この変更を知らなかった人や、頑なに古い暦に従い続けた人たちは「4月1日が新年」と思い込んでお祝いをしていました。そんな人たちに対して「April Fool(4月のバカ)」というあだ名がつけられ、からかいの対象になったというわけです。
でも、春の到来を祝う古代の祭りが起源という説もあります。ローマのヒラリア祭(3月25日頃)や、インドのホーリー祭(色粉を投げ合って楽しむお祭り)との類似性を指摘する声もあるんですよ。
世界各国のエイプリルフールの楽しみ方
フランス:「4月の魚」でいたずら!
フランスでは「Poisson d’Avril(4月の魚)」と呼ばれています。紙で作った魚の形を人の背中に貼り付けるというシンプルないたずらが伝統的。なぜ「魚」なのかは諸説ありますが、4月に魚が産卵期を迎え、簡単に捕まえられることから「簡単に騙される人」を表すようになったという説が有力です。
イギリス:正午までが勝負!
イギリスでは「April Fool’s Day」として親しまれていますが、実はいたずらができるのは正午までという独自ルールがあります。正午を過ぎていたずらをすると、「April Fool yourself(お前こそバカだ)」と返されてしまうんだとか!
スコットランド:2日間続くいたずら祭り
スコットランドでは「Hunt the Gowk(おバカ狩り)」として、2日間いたずらが続きます。1日目は人を使いに出して無意味なメッセージを届けさせ、2日目は「Tailie Day」として人の背中に「Kick Me」などのメッセージを貼るんです。スコットランド人、いたずら好きですね!
日本:メディアの日?
日本にエイプリルフールが伝わったのは明治時代と言われています。当初は「四月馬鹿」と訳されていましたが、今では「嘘の日」として定着。特に日本では、企業やメディアが公式に嘘の発表をする日としての側面が強いかもしれませんね。
忘れられない!有名なエイプリルフールのいたずら
世界には、大規模なエイプリルフールのいたずらがたくさんあります。中でも有名なのはBBCが1957年に放送した「スパゲッティの木」の特集。スイスの木にスパゲッティが生えていると真面目に報道し、視聴者から「どうやったらスパゲッティの木を育てられるか」という問い合わせが殺到したそうです。
1998年にはバーガーキングが「左利き専用ワッパー」を発表。左から右へとかぶりつけるように具材の配置を180度回転させた商品を紹介し、話題になりました。
なぜ私たちはいたずらを楽しむの?
心理学的に見ると、いたずらは社会的な結びつきを強める役割があるんです。「共有された笑い」は人間関係を深め、緊張を和らげる効果があります。また、日常の真面目な規則から一時的に解放される「カーニバル的な時間」として、人々に新鮮な気持ちをもたらすという説もあります。
最後に
エイプリルフールは単なる「嘘の日」ではなく、長い歴史を持った文化的な習慣なんですね。今年のエイプリルフール、まだ誰かをだましていない方は、この記事を読んでインスピレーションを得てみてください(ただし、相手を本当に傷つけるようないたずらはNG!)。
皆さんは、どんなエイプリルフールのいたずらが印象に残っていますか?コメント欄で教えてくださいね!
あ、ちなみにこの記事の内容は全部本当です。嘘じゃないですよ!…って言ったら、それこそエイプリルフール?