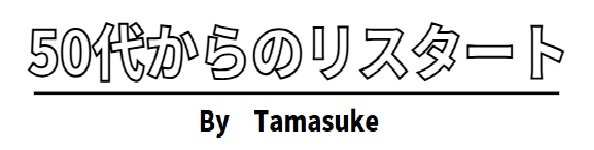こんにちは!今回は、最近じわじわと話題になっている「ETCの義務化」について取り上げてみました。
普段から高速道路をよく使っている人はもちろん、「たまにしか乗らないから関係ない」と思ってる方もちょっと待ってください。実はこのETC義務化、じわじわとすべてのドライバーに影響してくるかもしれないんです。
「えっ、いつからなの?」「何がどう変わるの?」「まだETC付けてないけど大丈夫?」という疑問に、できるだけわかりやすく答えていきます!
ETC義務化ってそもそもどういうこと?
まず、「ETC義務化」ってなに?というところから。
今までは、高速道路の料金所で「ETCレーン」か「一般レーン」を選べるスタイルでしたよね。でも、国の方針としては今後、ETCしか使えない道路や料金所が増えていく予定です。
つまり、「ETCがなければ通れない道」が登場するということ。これが“義務化”と言われているゆえんです。
ETC義務化はいつから始まるの?
では本題。「ETCの義務化っていつから始まるの?」という疑問ですが、現時点(2025年春)での国の発表や方針では以下のようになっています。
● 本格的な義務化は、2025年度以降の新設道路からスタート
国土交通省は、「新しく整備される有料道路(主に地方部や都市周辺部)」では最初からETC専用にする方針を打ち出しています。
すでに例も出ていて、宮城県の三陸自動車道や、首都高の一部では「ETC専用料金所」が運用開始済み。徐々にですが、確実に広がってきています。
● 既存の高速道路も、将来的にはETC専用へ?
今のところ「全国一律で義務化!」という話ではありませんが、将来的には既存の高速道路でも、ETC専用化を進めていく方針です。
ただし、「いきなり明日から!」というわけではなく、段階的に、かつ周知期間も設けられるので、いまのうちに準備しておけば慌てなくてすみます。
なぜETCを義務化するの?
「なんでわざわざETCを義務化する必要があるの?」
こう思う方も多いと思います。確かに今まで通り、現金やクレジットで料金を払う方法でも困らなかったわけですし、わざわざ制度を変えるのって面倒ですよね。
でも、国がETCの義務化を進めようとしているのには、ちゃんと理由があるんです。ポイントは主に3つ。それぞれもう少し詳しく見てみましょう。
① 渋滞の緩和とスムーズな通行
ETCの最大のメリットといえば、やっぱり料金所をノンストップで通過できること。
これ、地味にすごくて、特に大型連休やお盆・年末年始など、混雑するタイミングで大きな効果を発揮します。
実際に、ETCの普及が進んでからというもの、以前よりも料金所の渋滞はずいぶん緩和されているんです。
でも一方で、まだ「一般レーン」が残っていることで、ETC車も一般車に引っかかってスムーズに通れないこともあるんですよね。
ETC専用にすれば、すべての車が同じスピードで料金所を通過できるようになる。これにより、全体の流れがよくなり、渋滞の発生も抑えられるというわけです。
道路会社にとっても、ドライバーにとっても「スムーズな移動」が叶うなら、これは大きなメリットですよね。
② 人手不足への対策(無人化・省人化)
もうひとつ大きな理由が、「人手不足」です。
料金所では、24時間体制でスタッフが配置されていることが多いんですが、これって実はかなりの人件費がかかっています。
さらに最近は、どの業界でも人手不足が深刻化していて、若い世代の就業希望も少ないのが現実…。
そんな中で、ETCによる無人運用ができれば、大きなコスト削減になります。
- 料金所スタッフの配置が不要に
- 夜間や地方の料金所も無人化が可能に
- 労働環境の改善にもつながる
こういった背景から、「ETC専用にすれば、運営側も助かるし、利用者も待たずに済む」=一石二鳥というわけなんです。
実際、最近オープンした一部の道路では完全無人・完全ETC化が進んでいます。今後このスタイルが主流になる可能性は高いですね。
③ ETCの利用率がすでに高い
そして意外と知られていないかもしれませんが、ETCの普及率って、すでに90%超えなんです!
つまり、ほとんどのドライバーがもうすでにETCを使っているということ。
この数字を見ると、「じゃあもう、全体的にETCで統一してもいいよね?」という流れになるのは自然なことかもしれません。
ただし、残りの10%には、
- 高齢のドライバー
- たまにしか高速を使わない人
- ETC機器をつけていないレンタカーや一部の業務車両
といった“少数派”も含まれています。
そのため、「完全義務化」は段階的に慎重に進められているわけですが、国としては**「これだけ普及しているなら、いよいよ本格導入してもいいのでは?」**という判断をしているわけですね。
ETCがないとどうなるの?
ETC非搭載車の場合、ETC専用の道路や料金所を通れないということになります。具体的には、
- 通行できずに引き返しになる(場所によっては厳しい…)
- 通行前に特別な手続きが必要な場合もある(例:事前予約など)
特に、高齢者の方や、たまにしか高速を使わない人にとっては、ちょっとハードルが上がるかもしれません。
ETCをまだ付けていない人はどうすれば?
「うちはまだETCつけてないんだけど…」という方、大丈夫です。今からでも十分間に合います。
● ETCの導入手順(ざっくり)
- カー用品店やディーラーでETC車載器を購入
- セットアップ(車両情報を登録)
- 取り付け工事
- ETCカードを作る(クレジットカードまたはETCパーソナルカード)
工賃などは車種や店舗にもよりますが、1万〜2万円程度で導入できることが多いです。
● 補助金・助成制度もあるかも?
一部地域や時期によっては、ETC導入に対する補助金が出ることもあります。お住まいの地域の自治体や国交省の情報をチェックしてみましょう。
今後の動向にどう備える?
「ETCが義務化されるっていっても、今すぐ全部の高速道路がETC専用になるわけじゃないんでしょ?」
はい、その通りです。現時点ではすべての道路で一斉にETC専用になるわけではありません。でも、今後の国の方針や実際の動きを見ていると、着実に「ETC前提の社会」へと進んでいるのは間違いありません。
じゃあ、どう備えればいいの?という話を、もう少し具体的に見ていきましょう。
■ 新設される道路は“最初からETC専用”が基本に
国土交通省や高速道路会社の方針として、これから新しく整備される有料道路は、最初から「ETC専用」になるケースが増えています。
これは、
- 料金所の設置・維持コストが抑えられる
- 開通初日からスムーズな交通が実現できる
- 無人運営によって人手不足に対応できる
といった理由から、「はじめからETCありき」で作ったほうが効率的という判断なんですね。
実際に、2022年以降に開通した一部の地方道路や都市高速の入口では、すでにETC専用化された料金所が登場しています。「あれ?現金レーンないじゃん!」と驚いた人もいるのでは?
つまり、これから増えていく新しい道には、ETC非搭載だと通れない場所が確実に増えると考えておいた方がよさそうです。
■ 既存の高速道路も、段階的にETC専用へ?
そしてもうひとつ注目すべきなのが、今ある高速道路の「ETC専用化」も徐々に進んでいるということ。
例えば、
- 首都高や阪神高速の一部入口でのETC専用レーン化
- 深夜帯・休日限定でのETC限定割引などの導入
- 一般レーンの縮小や廃止(例:2レーン→1レーン)
といったように、ETCを使うことが“当たり前”の流れに変わってきています。
また、将来的には「すべてのインターチェンジから現金支払いを撤廃する」なんて話も、遠くないかもしれません。
もちろん、国や道路会社も一気に変えるつもりはなく、移行には数年単位の時間がかかるでしょうが、**「いずれ来る未来」ではなく、「もう始まっている現実」**として捉える方が正解かもしれません。
■ いざという時に困らないために
このような流れの中で、「まだETCつけてないけど、まあ困らないでしょ」と思っていると、ある日突然、“通れない道”に出くわす可能性があります。
例えば…
- 急な出張でレンタカーを使うとき
- 家族旅行で初めて通る高速道路を使うとき
- 深夜や早朝で有人レーンが閉鎖されていたとき
そんなときに「しまった、ETCないじゃん!」となると、引き返すしかない…なんて事態も。
これ、けっこうストレスです。
だからこそ、**「使う予定がない今こそ、ETCを準備するベストタイミング」**なんです。いざという時に慌てないよう、余裕を持って準備しておくのが大人の余裕ってやつですね。
■ 今後は「ETCありき」の社会へ
これからの高速道路は、おそらく“ETCありき”で設計されていく時代に入っていきます。
- スムーズな通行
- コスト削減
- 人手不足対策
- データ管理の効率化
あらゆる面でETCがあるほうが便利ですし、国としてもそれを前提にしたインフラ整備を進めています。
だからこそ、「まだ付けてないけど、どうしようかな」と迷っている方は、このタイミングでETC導入を前向きに検討することをおすすめします。
まとめ:ETC義務化は確実に進んでいる。今からの準備がカギ!
いかがでしたか?
ETCの義務化は、「2025年度以降の新設道路」から始まり、ゆくゆくは全国の高速道路に広がっていく見込みです。まだETCを付けていない方も、焦らず、でも早めに準備しておくと安心です。
普段使わない人ほど、急な旅行や仕事で高速道路を使うタイミングで「しまった!」となりがち。ちょっとの準備で、未来の安心が手に入るならやっておく価値アリです!
ではでは、快適なドライブを〜🚗💨